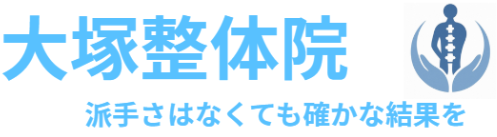スマホと脳
スマホ脳
著者 アンデシュ・ハンセン
整体院とは直接的な関係性があるわけではありませんが健康に影響を与えるものとして興味深い本なのでまとめていきたいと思います。
現代社会の不調の原因としても一読したい
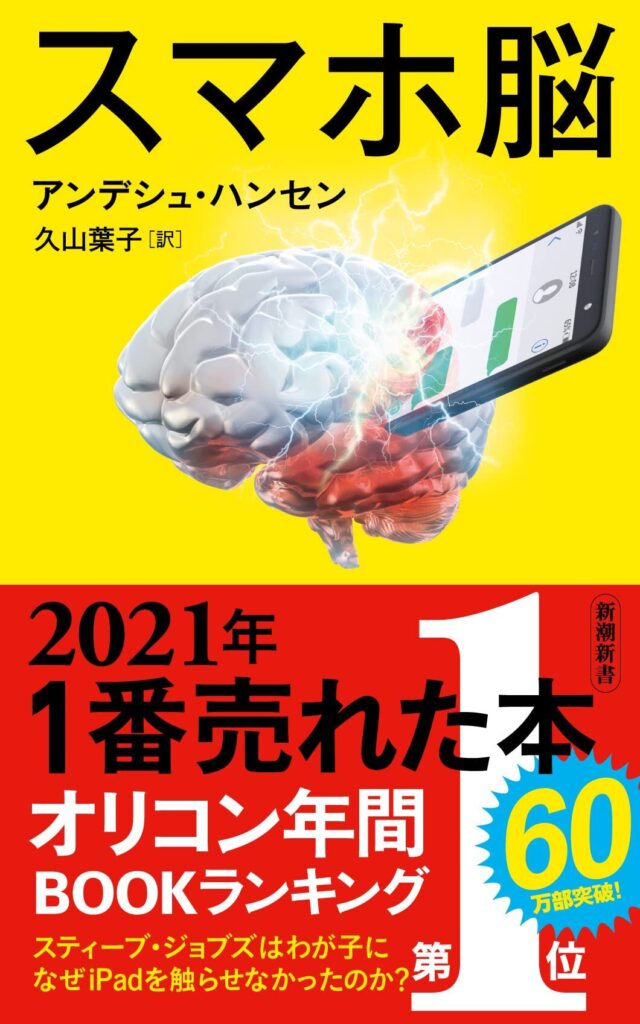
『スマホ脳』は、現代社会のスマホとSNSへの依存が、脳の進化に合わない環境であるため、私たちの集中力、記憶力、睡眠の質を低下させ、不安や抑うつを引き起こすと警鐘を鳴らす本です。
脳の報酬システムを刺激するスマホの仕組みと、その結果として心身に悪影響が出るメカニズムを解説し、運動や睡眠時間を増やし、スマホ利用時間を制限することを解決策として提案しています。
まず初めに多くの人がスマホを一日平均2.3時間ほど触っています。さらに6時間以上スマホを見ている人は、10分抑制するだけでストレスホルモンが上昇してしまいます。1日24時間の大切な時間でもかなりの割合を占めていると思います。
なぜ多くの人がスマホを手にして熱中してしまうのか?
脳からドーパミンが出ることによるものだと考えられています。
ドーパミンとは、脳内で働く神経伝達物質であり、「幸せホルモン」の一つです。
主な役割は、快感や幸福感をもたらし、意欲や集中力を高め、運動調節や記憶、学習に関わります。
さらにアルコールや薬物、ギャンブルなどの快楽に強く関わるとも言われており、過不足がパーキンソン病やADHD、統合失調症などの疾患と関連しています。
パチンコなどのギャンブルは、確実に当たるよりもしかしたら当たるなどの方が当たった時のドーパミン分泌が多いとも言われております。
=何かが起きるかもしれないということが1番行動力を高めることになります
さらにスマホによって人々の集中力を下げてします
基本的に人は一度に一つのことしか集中できない、マルチタスクは、ながら作業で実際は、2つのタスクを行ったり来たりしているだけである。またポケットにスマホが入っているだけで集中力を欠いてしまう。テーブルの上にスマホがあると意識もそちらに行ってしまう。実際に視界にスマホがあるだけでも影響を与えてしまう
スマホは、不眠になる
スマホやパソコンのブルーライトにはメラトニンの分泌を抑えてしまう作用がある
メラトニンは、暗闇に反応して脳から分泌されるホルモンです。 メラトニンは、概日リズム(サーカディアンリズム。 24時間体内時計)のタイミングを整え、睡眠をサポートします。 夜間に光を浴びると、メラトニンの分泌が阻害されます。
パソコン、スマホがない時代は、ブルーライト=晴れ渡った空から降り注ぐものであった
部屋の中にあるだけでも不眠に影響を与える頭では、そこにスマホがあることを理解しているので影響を与える。
実は、Appleの創業者スティーブ・ジョブズ、マイクロソフト元CEOビルゲイツは、自身の子供たちにスマホの使用時間に制限をかけている
自分たちが提供しているものがどれだけの影響と中毒性を持っているのかを理解している
対応策は、運動すること
運動した後は、集中力が増す
先祖が狩りをしていた時代には、よく動いていた動くことで危機回避、狩猟を行っていた
スマホが脳に与える具体的な影響まとめ
- 集中力・思考力の低下:浅く考える機能が低下し、物忘れやミスが増え、思考力や判断力、意欲が低下します。
- 睡眠障害:スマホのブルーライトが睡眠を誘うメラトニンの分泌を抑制し、寝つきを悪くします。
- 依存性:スマホの不確実な情報や通知が脳の報酬系を刺激し、ドーパミンを放出させることで、スマホへの依存を招きます。
- 不安・抑うつ
SNSを利用している人ほど孤独感が高く心の健康が失われやすい自分よりも優秀な人がすぐに見つけられてしまい劣等感を抱いてしまう。
スマホ管理するポイント
・スマホでなくて良いものは使わない
・メール、LINEのチェックは時間を決める
・通知をすべてオフにする
・スマホの画面をモノクロにする
・スマホを寝室に置かない:脳の疲労を避けるために、スマホの利用時間を減らし、寝室に置かないことも有効。
・誰かと会っている時はスマホを出さない