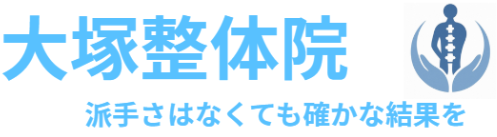大塚整体院では主に構造医学という学問をベースに診療を行います。
構造と聞くと人体構造を想像すると思いますがそれだけではなく構造主義という意味を含んでいます。
一言でいうと人間の行動や思考は、目に見えない構造に左右されているということです。
哲学的な意味合いも含まれていて医療の分野に取り入れられています。
また物理学を医療に取り入れ人体を解析し、その包括的な手段として構造主義を用いるものとなります。
医学の本質である「人の健康に資する」という目的を見定め、40年以上にわたる伝統的な医療です。
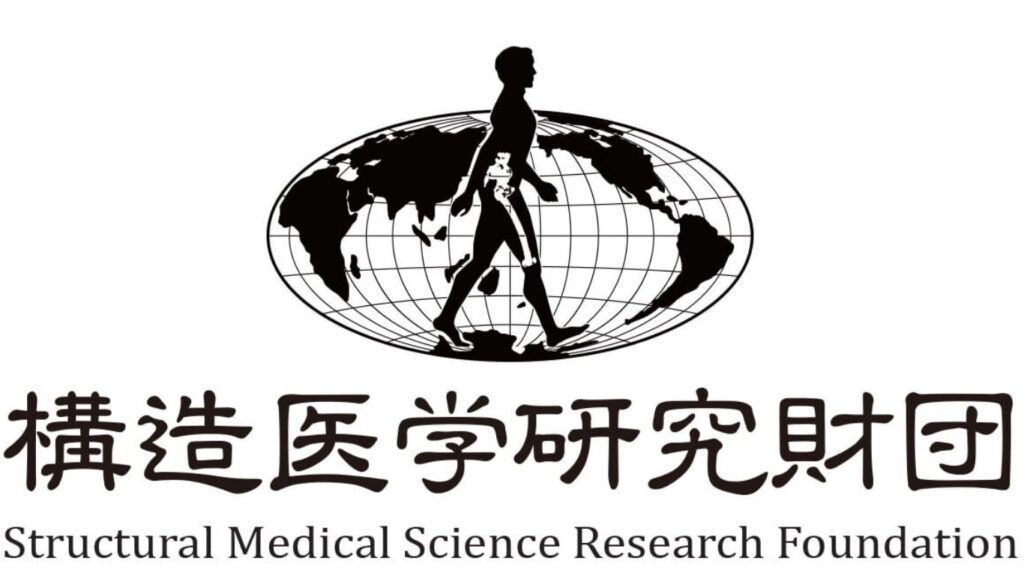
「構造医学」は、一般の方は、ほとんどの方が聞きなれないと思いますので少し詳しく説明させていただきます。
【構造医学の特徴】
体への負担が最小限
構造医学の治療は、無理に捻る、引っ張る、押す、叩くなど体に負担のかかることをしません。
症状の原因を明確にして整復の方向や加減を調整しわずかな力で整復をしていきます。
また構造医学の治療は生理性を大切にします。生理性とは、「体の正常な働きに基づくもの」という意味があります。小さな力で整復をかけるため患者さんに過剰な負荷をかけることなく痛みのない治療が可能となります。
検査=治療という考え方
当院で行う「構造医学的検査(スクリーニング検査)」は、単なるチェックではありません。
検査そのものが「治療」につながるのが大きな特徴です。スクリーニング検査では、体に適正な圧力を加えながら状態を確認していきます。
その過程で関節の潤滑が促され、自然と関節の整復(正しい位置への整復)が起こります。
つまり、検査を受けるだけで治療が進んでいくのです。
また、痛みが出ている箇所が必ずしも原因とは限りません。
全身を丁寧に検査することで、原因を見極めながら、体に余計な負担をかけることなく整復を行います。
一方で、無理に引っ張ったり、ねじったりする検査は体を傷めてしまうこともあります。
当院ではそうした方法は用いず、安全かつ的確に「検査=治療」を実現していきます。
特殊な治療器具
人は道具を使うことで様々なことを可能にしてきました。
例えば、肉眼では確認できない物の観察には顕微鏡を使い、声の拡張にはスピーカーを使い遠くの人、モノに届けます。
人は、道具の発達とともに生活や文明が発展してきました。道具を使うことでできなかったことを可能にしていきます。
治療には専用の器具を使います。
手技と言われますが人の手でやるよりも治療器具を正確に使いこなせるようになることが治療効果を最大限に高めることにつながると考えております。感触等細部に至るより高度な治療を可能にしています。


【構造医学の治療法】
関節に圧力をかける骨盤整復、各関節整復
人の体には、約260の関節があります。
骨と骨のつなぎ目である関節は、そもそもの体の動きを可能にする重要な役割があります。
その中で骨盤は、「仙腸関節」「恥骨結合」など複数の関節で支えられている部分です。
姿勢や動作、過去の外力の影響により微細なズレを起こします。特に仙腸関節は数ミリ単位の動きです。
そんなわずかな変位でも腰痛、股関節痛、歩行不良につながるため、生理的な可動範囲内で圧を加えて正常な位置と動きを取り戻す必要があります。
整復には無理な力を加えるのではなく方向と圧の角度で整復をかけていきます。
骨盤だけでなく各関節の整復も必要に応じて行います。「無理に動かす」ものではなく関節の自然な動きを取り戻すことで痛みや不調を排除することができます。

リダクターによる矯正
リダクター矯正とは、特殊な器具「リダクター」を用いて、背骨や骨盤の歪みを整える施術です。背骨のS字カーブをなだらかにし、狭窄した部分を広げる効果があります。また、姿勢改善や、首の寝違え、腰痛などの改善も期待できます。
リダクター矯正の特徴
■背骨の歪みを専門的に改善→特殊なローラー(リダクター)を使い脊椎の配列を整えます。脊椎を起こし姿勢改善します
■血流促進、脊髄液の循環を促します→脊椎にリダクターをかけると血液、脊髄液の流動が生まれ循環が起こります。
循環が悪いと自然治癒力が最大限発揮されません。
■バキバキしない矯正→特殊な器具を使うことで、身体への負担を最小限に抑え、ソフトな矯正を行います
■筋肉、骨格の同時に施術を行う→体は、全身がつながっていますので文節ごとに分けずに大きな枠で対応していきます。
生理的局所冷却法
生理的局所冷却法、聞き慣れない言葉だと思います。冷やす、温めるどちらがいいのか?
答えは、冷やすことです。もちろん冷やし方にもよりますが、、、
基本的に温めることによりタンパク質構造は、破壊されていきます。逆に体を悪くしてしまいます。
冷却することにより熱によるエントロピー増大を抑えることができます。
物体が活動を行えば熱が発生します。熱により痛みを発生させ体の不調を招きます。熱を下げるためには局所的な冷却が必要です。
局所というのがポイントで全体の中の一部を冷やすことにより相対的に一部の温度が低くなります。
下がった部位を回復させようとする働きが起こります。逆に温めてしまうと上げた温度を下げようとエネルギーを使います。その分回復がおくれてしまいます。


【突き詰めたい治療法】
私が構造医学にこだわる理由の一つは、学びを深めれば深めるほど、他の治療法を理解し説明や予測ができるようになるからです。
多くの治療法は「この方法をこのように行う」といったHOW-TO(やり方)が中心です。
ですので、教わったこと以外の治療を見てもなかなか本質的な理解には至りません。
しかし、治療の根幹には必ず基礎となる考え方や理論があります。構造医学を学び進めることで、その基礎へとつながり、どんな治療法もより深く理解できるようになるのです。
構造医学に出会って6年以上経ちますが、学べば学ぶほど果てしない世界だと実感しています。
同時に、この道を極めた先にどのような景色が広がっているのか、楽しみでもあります。
治療において「学び終わり」というものはなく、生涯を通じて研鑽を重ね、技術を磨き続けたいと考えています。
身体の不調や痛みに悩まれている方の症状を和らげ、健康を取り戻すことが私のやりがいです。
どんな小さなお悩みでも、お気軽にご相談ください。