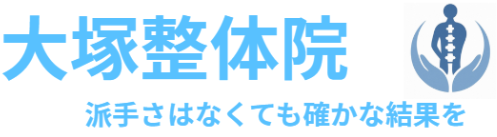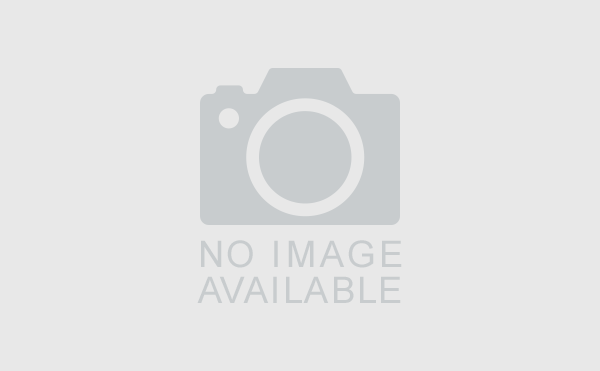痛みとは?
私たちが日常で感じる「痛み」は、ただの不快な感覚ではなく、体が発する重要な警告信号です。
生理学や解剖学の視点から痛みを理解することは、単なる症状の緩和ではなく、根本的な原因へのアプローチにつながると考えます。
痛みの定義
国際疼痛学会(IASP)は痛みを以下のように定義しています。
「痛みは、実際の組織損傷またはその可能性と関連した、あるいはそのように表現される不快な感覚および情動体験である」
つまり痛みは感覚と情動の複合体であり、
脳が体の状態を評価して「危険」と判断したときに生じる現象です。
解剖学・生理学的視点
痛みは主に侵害受容器によって感知されます。

侵害受容器は皮膚、筋肉、関節、内臓など体中に分布しており、物理的刺激や化学的刺激、熱刺激を感知します。
侵害受容器が刺激されると、一次求心性ニューロンを介して脊髄に信号が送られます。脊髄後角で情報が変換され、必要に応じて抑制や増幅が行われます。
その後、視床を経由して脳の体性感覚野や前頭前野、扁桃体などに到達し、「痛み」として認識されます。
ここで重要なのは、痛みは脳で知覚される主観的体験であり、単に末梢の損傷だけで決まるわけではないことです。
痛みの伝達には、主に2種類の神経線維が関わります。
1. Aδ線維:太くて速い線維で、鋭く短い痛み(例えば針で刺されたような痛み)を伝えます。
2. C線維:細くて遅い線維で、鈍く持続する痛みや不快感を伝えます。
脊髄での情報処理には「ゲートコントロール理論」が関与し、他の感覚刺激や心理的要因によって痛みの強さが変化します。
さらに慢性痛では、神経回路の過敏化や脳の可塑性によって、痛み信号が強化されてしまうことがあります。
長く続く痛みには、この原理により体の状態は改善しているのに痛みが残る方がいるのも事実です。
まとめ
痛みは単なる感覚ではなく、生理学的・解剖学的に複雑な情報処理の結果として生じる体の警告信号です。
痛みを正しく理解することで、表面的な対処ではなく、原因に基づいた根本的な治療への道が開けます。
さらにこのようなお悩みのある方は、当院でお役に立てると考えております
•2つ以上の整骨院や病院に行ったが良くならなかった、効果を感じられなかった
•回数券の押し売り、サブスク契約、何十万円もする物販の営業をされて嫌な思いをした
•担当者が毎回変わり治療の内容が薄く信頼できる先生に診てもらいたい
•自分の身体の状態を理解してしっかりと治していきたい
上記のお悩みがございましたら一度ご相談ください。
また「これは診てもらえるのかな?」という疑問も、お気軽にお尋ねください。
早期にご相談、対応できれば手術を回避できるケースもあります。
今回もブログにお付き合いいただきましてありがとうございます。
私の治療や経験が皆様に役立つことがあれば幸いです。