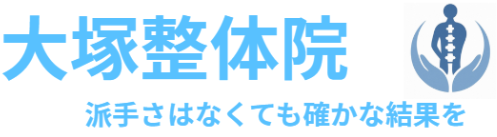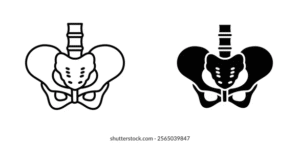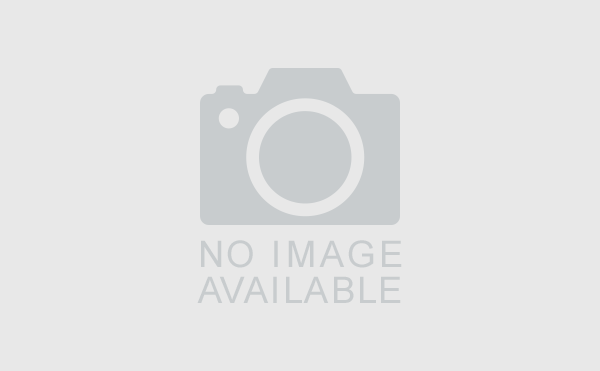痛み・不調はなぜ起こるのか?
私たち人間の体は、重力の影響を受けながら生きているという事実を忘れがちです。
生まれた瞬間から、地球の重力は私たちを常に地面に引きつけています。
この「重力」という存在を無視して体を理解することはできません。構造医学は、この重力と生体の関係を重視し、「痛み」を物理学的、生理学的、解剖学的に捉えることから始まります。
重力をとらえるという表現をします
重力と生理性の関係
人間の体は、重力下で最も効率よく立ち、動き、生活できるように設計されています。
この「自然な状態」を構造医学では生理性と呼びます。
生理性が保たれている時、筋肉や関節、神経は無理なく働き、痛みは起こりません。しかし、日常のクセや不良姿勢によってこの生理性が崩れると、体の構造はバランスを失い、どこかに過剰な負担がかかります。
物理学で見る体の歪み
物理学的に考えると、私たちの体は重力線に対して垂直に立つことで最も効率が良くなります。
例えば骨盤が傾けば、重力線と体の中心線はズレます。
その結果、膝や腰、首などにてこ作用やモーメントが働き、特定の部位にストレスが集中します。この状態が長引けば、組織は,
摩耗し炎症を起こして痛みというシグナルを発するのです。
では、体の歪みを検知している部分はどこなのか?
2か所あります。
1、仙腸関節
2、顎関節


2つの機能により重力を検知しバランスを保つようになっています。
2つの機能が様々な要素で機能が低下した時に不調が起こり始めます。
例えば、過去の怪我(既往歴)、日常生活動作により負荷をかけた時、顎関節ならば歯科矯正などがあげられます。
解剖学的視点からの痛み
痛みは「そこに異常がある」から起きるのではなく、「構造が本来の位置を失った結果、負荷が集中している」ことが多いのです。
腰痛を例に挙げると、腰椎そのものに問題があるケースはごく一部で、実際には骨盤や仙腸関節の機能低下が原因であることが多いと考えられています。
つまり、痛みを取るためには「腰をマッサージする」「腰の治療をする」だけでは不十分で、重力下での体のバランスを取り戻すことが根本改善につながります。
まとめ
痛みは体からの警告です。
しかし、その原因は「痛む場所」ではなく、体の構造が重力との調和を失ったことにあります。
だからこそ、構造医学では、骨格・関節・筋肉の働きを「重力」「物理学」「生理性」に基づいて分析し、解剖学的な整合性を持たせながら施術します。
「痛みを取る」だけでなく、「痛みを生まない体」を作る。それが施術において大切なことです。
さらにこのようなお悩みのある方は、当院でお役に立てると考えております
•2つ以上の整骨院や病院に行ったが良くならなかった、効果を感じられなかった
•回数券の押し売り、サブスク契約、何十万円もする物販の営業をされて嫌な思いをした
•担当者が毎回変わり治療の内容が薄く信頼できる先生に診てもらいたい
•自分の身体の状態を理解してしっかりと治していきたい
上記のお悩みがございましたら一度ご相談ください。
また「これは診てもらえるのかな?」という疑問も、お気軽にお尋ねください。
早期にご相談、対応できれば手術を回避できるケースもあります。
今回もブログにお付き合いいただきましてありがとうございます。
私の治療や経験が皆様に役立つことがあれば幸いです。