整骨院、整体院は、もちろん病院、医療機関を受診すると必ず検査が行われる。
これは、当然のことであると思います。
※一部の整骨院、整体院では、そういう医療的な検査は、まるで行われずいきなり施術が行われることがありますが、、
また、検査と一口に言ってもいろいろなものがあります。
①視診(レントゲン検査を含む)
②触診
③動的触診(モーションパルペーション)
④ROM
⑤その他
それぞれの問題点と内容
①視診は、参考的な意味合いしか持たずレントゲンも三次元的な影響を発見することは、難しい
②触診は、重要な意味を持っているが熟練度により差が出る。触診時の体位、環境が影響してしまう動的な観察には、乏しい
③動的触診は、かなり優秀な診断法と言えるが熟練度による差が起きる。また病的な範囲と生理的な範囲の境界が個体差が出てしまうことが考えられる
④参考角度はあるが、相対的な運動にて評価してしまう。各運動単位の判断が難しい
例えば、過多可動域と過少可動域が同時に存在すると総和として正常に見えてしまうことがある
⑤生理運動に重力要素を考慮したものが少ない
上記に対して私の行う検査方法についてまとめておきたいと思います。
重力要素、生体潤滑理論、レバーアーム理論、エネルギー保存則、カンナ効果、流体力学理論を用いて侵襲性の少ない方法を取り入れている
近年、体に無理な検査、意味を持たないものが増えている現状が考えられる。
逆に検査をしたから悪くなったともいわれるものもあると考える
自身は、無理なことをして患者さんを傷つけたくないと考える
わかればわかるほど、勉強すればするほど、考えるようになり危険な行為が見えてきているつもりである。
そこで取り入れているのが、重力要素を考慮し見立てを立てていくこと
実際に普段の生活では、必ず1Gを重力を受けている
重力を基準に体がどのような影響を受けているのかを脊椎各分節(4つの分節)ごとに見ていく
また、それに伴い外傷歴、生活習慣、就寝姿勢等を聞き問題を発見することができる
侵襲を少なく、正確さを求め、また検査から病を未然に防ぐことを大切に診療に臨んでおります。

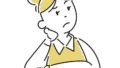
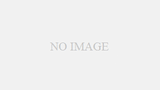
コメント